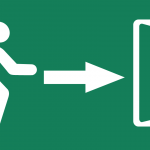キュービクルは、高圧で送られてくる電力を安全に低圧へ降圧し、商業施設や工場、オフィスビル、学校、病院などへ安定供給するための重要な変電設備です。契約電力が50kWを超える事業者には設置が義務付けられており、電力インフラを支える基盤として欠かせません。今回は、キュービクルの仕組みや種類、そして内部構造をわかりやすく解説します。
キュービクルとは
キュービクルは、高圧で送られてくる電気を100Vや200Vへ変換し、建物内に安全かつ効率的に配電するための変電設備です。発電所から施設までは6,600Vの高圧で送電されますが、そのままでは一般の機器では利用できないため、キュービクルによる降圧が不可欠となります。
商業施設や工場、オフィスビルなどの中規模から大規模建物で広く採用され、安定した電力供給を支える中核的な役割を担っています。特に契約電力が50kWを超える事業者には、高圧受電設備の設置が法令で義務付けられています。
キュービクルの仕組み
キュービクルは、高圧で受けた電力を低圧に変換し、保護や計測を行いながら安全に配電する仕組みを備えています。ここでは、どのようにして電圧を変換しているのか、契約区分による違い、さらに電力供給を効率化するための基本的な考え方について解説します。電気の利用規模に応じて受電方式は変わるため、その仕組みを理解することは非常に重要です。
先ほど解説したように、キュービクルは高圧で受電した電力を100Vや200Vといった低圧に変換し、日常的に使える形にするための装置です。受電から変圧、保護、計測、配電までを一体で行い、停電やトラブル時にも影響範囲を最小限に抑えられるよう設計されています。
発電所から送られてくる電気は6,600Vの高圧ですが、このままでは家庭用機器や一般設備では利用できません。そこでキュービクルを設置し、電圧を適切なレベルに変換することで、安全かつ効率的に電力を供給できるようになります。
電力の受電契約には「低圧受電契約」と「高圧受電契約」の2種類があります。
- 低圧受電契約(50kW未満):家庭や小規模オフィスなど、小規模施設向けの契約
- 高圧受電契約(50kW以上2,000kW未満):工場や商業施設など、大きな電力需要を持つ施設向けの契約
電気の使用量が多くなるほど、高い電圧で受電する必要があります。これは以下の電力の基本式で説明でき、同じ電力でも電圧を高くすると電流を抑えられるため、配線の発熱損失を減らせます。
- 電力(W)=電圧(V)×電流(A)
ただし、高圧のままでは機器に直接利用できないため、キュービクルで100Vや200Vに降圧して、安全に使用できるようにします。特にエアコンやIHクッキングヒーターのように200Vで稼働する機器にとって、キュービクルによる適切な電圧変換は欠かせません。
なお、用途に応じて末端の電圧降下を見込んだ運用(例:105Vや210V)を選ぶこともあります。
キュービクルの種類
キュービクルは、主遮断装置の方式によって大きくCB形とPF・S形の2種類に分けられます。それぞれ構造や性能、適用される施設規模が異なるため、用途に応じた適切な選定が必要です。
CB形
CB形は、遮断器(Circuit Breaker, CB)を主遮断装置として採用する方式です。遮断器は異常電流を検知すると自動的に回路を遮断でき、平常時の開閉操作にも対応します。
復旧が速く、保守性や安全性にも優れることから、300kVA以上の電力を必要とする病院や重要インフラ施設など、安定供給が特に重視される場所で多く利用されています。
遮断器には次の種類があり、設備規模や運用方針に合わせて選定されます。
- ガス遮断器
- 油遮断器
- 空気遮断器
ガス遮断器
ガス遮断器は六フッ化硫黄(SF₆)ガスを用いてアーク放電を消滅させる方式で、高い絶縁性能を持ち、大電流・高電圧設備に適しています。コンパクト化や安定性に優れますが、ガス管理に注意が必要です。
油遮断器
油遮断器は絶縁油を利用して消弧作用を発揮する方式で、古くから用いられ信頼性があります。ただし、油漏れや火災リスクがあり、定期メンテナンスが不可欠です。
空気遮断器</h4
空気遮断器は圧縮空気でアークを消滅させる方式で、環境負荷が小さく保守が容易という利点があります。ただし遮断性能は他方式に劣るため、中小規模設備での利用が中心です。
近年の高圧受電設備では、真空中でアークを消滅させる高圧真空遮断器(VCB)が主流です。長寿命で安全性が高く、メンテナンスも容易なことから幅広く採用されています。
PF・S形
PF・S形は、高圧限流ヒューズ(PF)と高圧交流負荷開閉器(LBS)を組み合わせた方式です。PFは過大電流時に内部のエレメント(銀線)が溶断して遮断し、LBSは回路の開閉を担います。
構造がシンプルで導入コストを抑えやすく、300kVA以下の小中規模施設で多く採用されています。ヒューズ溶断時には交換が必要ですが、省スペースで扱いやすいことが大きなメリットです。
キュービクルの内部構造
キュービクルは、高圧を受電して低圧に変換し、安全に配電するために複数の機器で構成されています。それぞれが電圧変換、計測、力率改善、過電圧保護、メンテナンス安全確保といった役割を担い、全体として安定した電力供給を支えています。ここでは、代表的な内部機器の機能と特徴を解説します。
- トランス(変圧器)
- 計器用変圧変流器(VCT)
- 電流計・電圧計
- 高圧進相コンデンサ(SC)
- 直列リアクトル
- 避雷器(LA)
- 断路器(DS)
トランス(変圧器)
高圧変圧器は、受電した高圧電力を100Vや200Vなど施設で利用可能な低圧に降圧する装置です。末端での電圧降下を考慮し、105Vや210Vで供給する場合もあります。変換は鉄心に一次巻線と二次巻線を設け、電磁誘導の原理で行われます。
絶縁方式の違いにより「油入トランス」と「モールドトランス」に分類されます。油入トランスは最も普及しており幅広い施設で利用され、モールドトランスはコンパクトかつ保守が容易ですが価格が高い傾向があります。
また、用途によって「単相」と「三相」に分かれます。単相は照明やコンセント用の100Vに、三相は生産設備や空調に必要な200Vを供給し、施設の需要に応じて適切に選定されます。
計器用変圧変流器(VCT)
計器用変圧変流器(VCT:Voltage and Current Transformer)は、使用電力量を安全に計測するための装置です。高圧の電流をそのまま測定するのは危険であるため、電圧変圧器(VT)と計器用変流器(CT)を組み合わせ、低電圧・小電流に変換して計測器に入力します。
電流計・電圧計
電流計・電圧計は、キュービクル内部の電流や電圧を測定する装置です。指示値を常時監視することで異常の早期発見につながり、ピーク電力の把握や省エネ対策に役立ちます。近年は力率や高調波も同時に確認できる多機能メータが普及しています。
そのほか、消費電力を測定する電力計、周波数を確認する周波数計、電力利用効率を示す力率計など、複数の計器が設置され、電気の状態を総合的に把握できるようになっています。
高圧進相コンデンサ(SC)
高圧進相コンデンサは、電力システムの力率を改善し効率を高める装置です。これにより無駄な電力消費を抑え、安定した電力供給と省エネ効果を両立できます。
方式は「ガス封入式」と「油入自冷式」があります。ガス封入式は絶縁油を使わず環境負荷が小さく寿命が長いため大規模施設向きです。油入自冷式は絶縁油で冷却性を確保し、小型軽量化とコスト面で優れる点が特長です。
直列リアクトル
直列リアクトルは、高圧進相コンデンサを設置した際に発生する高調波を抑制するための装置です。高圧進相コンデンサには「高調波」という不要な電流が流れ込む場合があります。高調波は装置の発熱や誤作動を招くため、直列リアクトルを接続して抑制します。
直列リアクトルは、高調波を低減して機器の誤作動を防ぎ、電力ロスを抑えて供給の安定性を高める役割を持ちます。コンデンサと組み合わせることで、安全で効率的な電力システムを実現できます。
避雷器(LA)
避雷器は、落雷や回路の開閉で発生する過電圧を大地に逃がし、設備を保護する装置です。瞬間的な異常電圧から電力設備を守るために欠かせません。
断路器(DS)
断路器(Disconnecting Switch, DS)は、試験・点検・修理の際に回路を安全に開放するための装置です。遮断器が誤って投入されても感電や事故を防ぐため、メンテナンス作業の安全確保に必須です。
キュービクルの交換時期・タイミングは?
キュービクルの交換は、原則として15年程度を目安に検討することが基本です。税法上の減価償却でも「電気設備(照明設備を含む)」の「その他のもの」は15年と定められており、更新計画を立てる際の基準として活用できます。
ただし、実際の更新は運用状況や劣化の進み具合を考慮し、15〜20年程度で判断することが一般的です。特に屋外設置や高温・多湿、粉じんや塩害といった厳しい環境では劣化が早く進むため、同じ使用年数でも前倒しの更新が求められる場合があります。その際は現場環境と劣化診断(絶縁抵抗・接触抵抗・温度上昇など)をあわせて確認することが重要です。
さらに、内部機器ごとに寿命が異なる点にも注意が必要です。本体よりも先に主要コンポーネントを更新するケースは珍しくありません。
交換時期を的確に見極めるには、定期点検の結果を計画に反映させることが欠かせません。電気事業法では、運用中に「月次点検」を実施し、併せて停電を伴う「年次点検」や精密点検を行うことが定められています。点検記録に劣化や異常の兆候が見られる場合は、部品交換や更新を早めに検討する必要があります。
結論としては、「15年を基本としつつ、環境・点検結果・内部機器の状態を踏まえて15〜20年の範囲で最適化する」ことが実務的な対応です。
まとめ
キュービクルは、6,600Vの高圧電力を受電し、施設で利用できる100Vや200Vへ安全に降圧して配電するための重要な設備です。遮断器の構造によってPF・S形とCB形に分類され、小規模から大規模施設まで用途に応じた導入が行われています。
内部には変圧器や高圧進相コンデンサ、直列リアクトルなど多様な機器が組み込まれ、電力の安定供給を支えています。さらに、寿命や劣化状況を踏まえ、15年程度を目安に交換計画を立てることが実務的です。
小川電機株式会社は、60年以上にわたって培った経験を活かし、キュービクルの新設から保守、トラブル対応まで幅広く対応しています。安心で持続可能な電力インフラを築くための信頼できるパートナーとして、ぜひご相談ください。