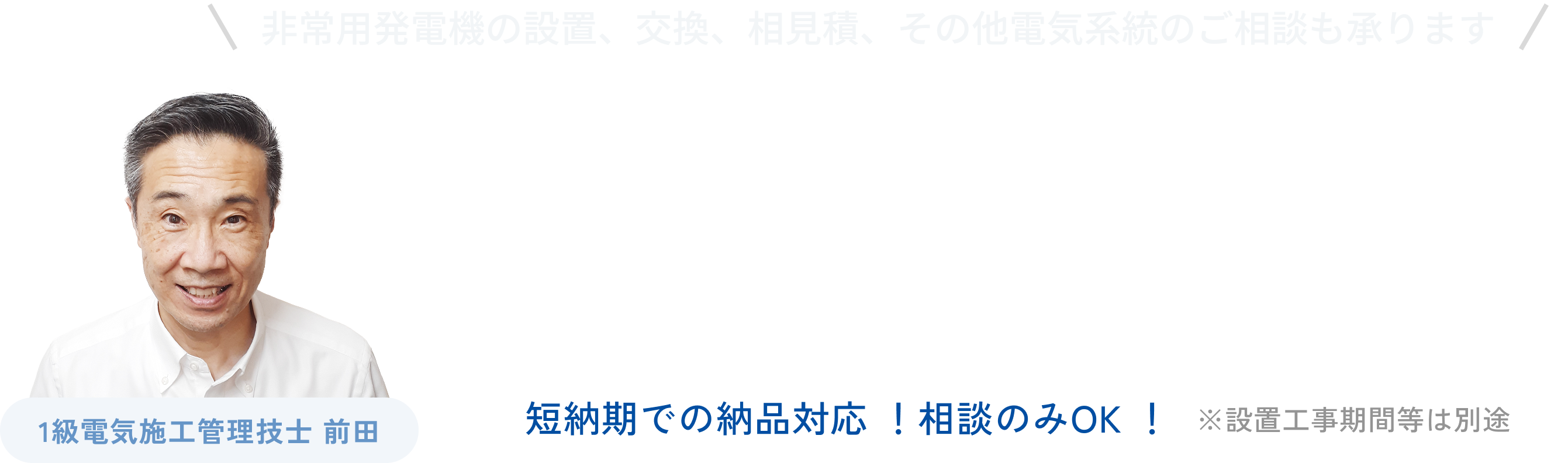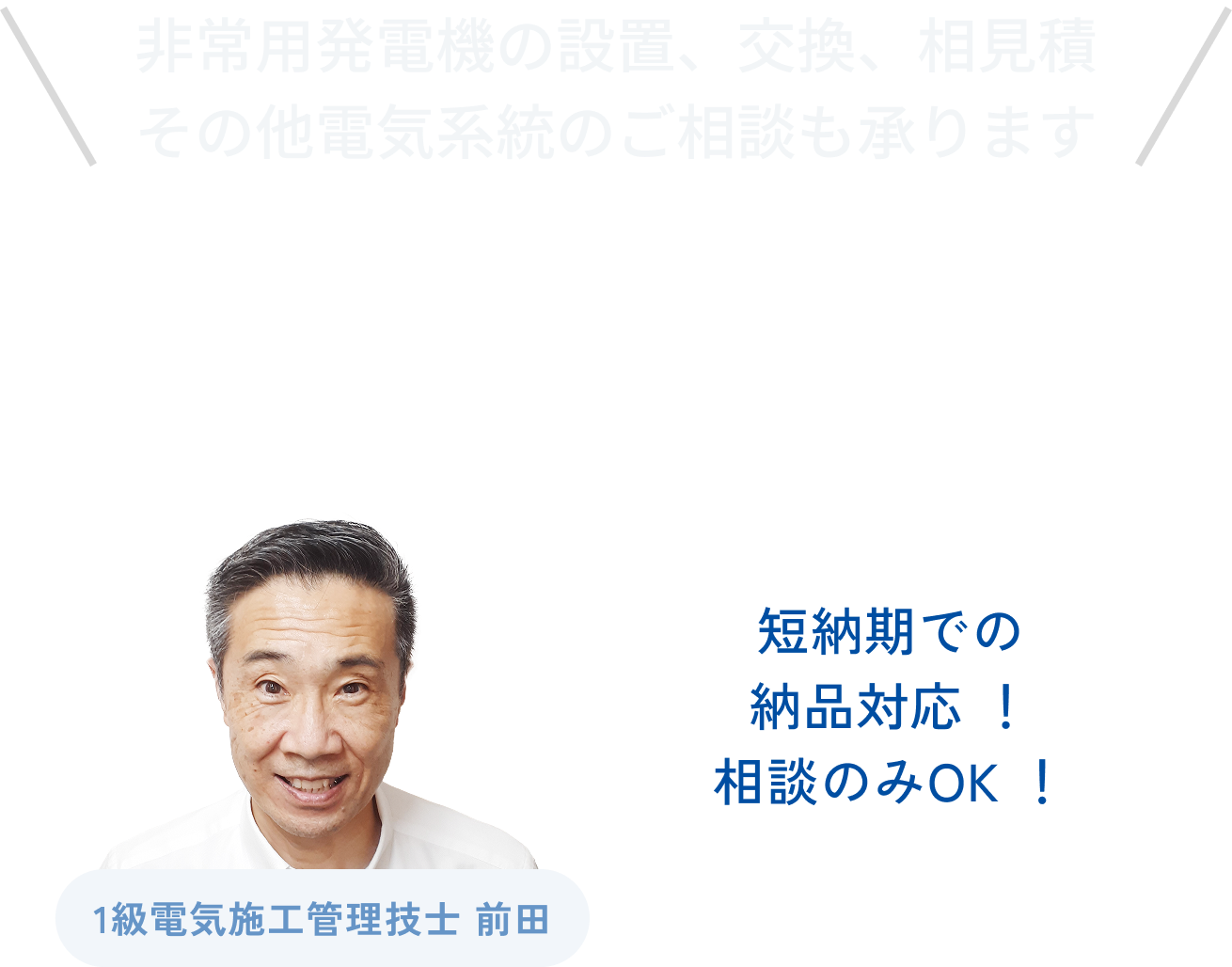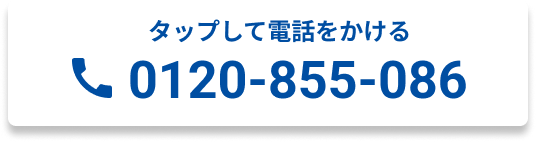非常用発電機は、災害や停電時に重要な役割を果たします。病院や商業施設、オフィスビル、工場などの施設には欠かせない設備であり、電力供給が途絶えると、病院では命に関わる問題が、工場では生産ラインの停止などの深刻な影響が発生します。そのため、非常用発電機は人命や経済活動を守るために不可欠な存在であり、さまざまな施設に導入されています。
導入するべき非常用発電機を選定するうえで、サイズの検討は欠かせません。必要な設置スペースの確保や、設置に向けた環境整備など、サイズに応じて取るべき対応が変わります。また、要求するスペックや設置場所の条件によって、導入できるサイズに制限がかかる場合もあります。
非常用発電機とそのサイズにどのような関わりがあるのか、よく理解しておくことで適切な種類の選定に役立ち、効率的な設備運用につながります。今回は、非常用発電機のサイズに関連する要素と、サイズが大きい種類を導入するうえでの注意点を解説します。
非常用発電機とは
非常用発電機は、災害や停電など非常時に備えて設置される発電設備であり、軽油やガスなどの燃料を用いて発電し、重要な設備へ電力を供給します。
本記事では非常用発電機のサイズに焦点を当てて解説しますが、まずは非常用発電機の基本的な役割や設置理由を押さえておく必要があります。はじめに、非常用発電機の果たす役割と導入の背景を解説します。
なお、非常用発電機には一般家庭向けの小型タイプも存在しますが、この記事では病院や工場などに導入される大型施設向けの設備を対象としています。
非常用発電機の役割
非常用発電機の役割は、常用電源が停止した際に防災設備へ電力を供給することです。
商業施設や病院、オフィスビルなどには、スプリンクラーや非常灯、非常放送といった防災設備が備えられています。これらは災害時に避難誘導や初期消火を行ううえで不可欠ですが、電力がなければ作動しないため、対応が遅れ被害の拡大につながるおそれがあります。
こうしたリスクに備えるため、非常用発電機は非常時に電力を安定供給し、防災設備の機能維持に貢献します。たとえば、火災で常用電源が喪失した場合でも、非常用発電機が稼働すればスプリンクラーや非常放送を作動させることができ、被害の抑制につながります。
このように、非常時に電力を供給する設備全般は「非常電源」と呼ばれ、その中でも燃料を使って自立して発電を行う設備が「非常用発電機」です。
非常用発電機の設置目的
非常用発電機の設置目的は、電力供給が断たれた際にも必要な設備へ電力を届けることです。
病院や商業施設、オフィスビル、工場など多くの施設で導入されており、その目的は施設ごとに異なります。ここでは、非常用発電機が設置される主な理由について解説します。
- 災害対策
- BCP対策
災害対策
災害対策は、非常用発電機を導入するもっとも代表的な目的です。前述のとおり、防災設備へ電力を供給することで、被害の拡大を防ぐための初期対応を可能にします。非常用発電機は、災害に備えるうえで欠かせない存在といえるでしょう。
特に下記の条件に該当する施設については、消防法や建築基準法によって非常用発電機の設置が義務付けられています。
◆非常用発電機の設置が義務付けられる施設の条件
準拠する法令 | 条件 | 該当施設の例 |
|---|---|---|
消防法 | ・不特定多数の人が出入りする・避難困難者がいる、もしくは避難が困難な環境条件である・床面積が延べ1,000m2以上 | 病院、老人ホーム、学校、工場、映画館など |
建築基準法 | ・高さ31mを超える・不特定多数の人が出入りする・避難困難者がいる、もしくは避難が困難な環境条件である | ホテル、マンション、オフィスビル、大型商業施設など |
ただし、これらの条件に該当しない施設でも、リスクに備えるため自主的に導入するケースが増えています。
非常用発電機は、法的義務の有無にかかわらず災害対策として重要な設備です。施設を運営されている方は、災害時のリスクを一度見直し、必要に応じて導入を検討してみてください。
BCP対策
BCP(Business Continuity Planning:事業継続計画)の一環として、非常用発電機が導入されるケースもあります。BCPとは、災害やシステム障害などの非常時において、事業を継続させるための計画のことです。
非常用発電機があれば、停電などによって電力が断たれた場合でも、自家発電により事業の早期復旧が可能になります。たとえば、工場であれば生産ラインの再稼働、オフィスビルであればサーバーの継続運転が実現できます。
このように、非常用発電機は事業活動の中断を最小限に抑えるための要であり、安全確保にとどまらず、経営の観点からも重要な設備となります。
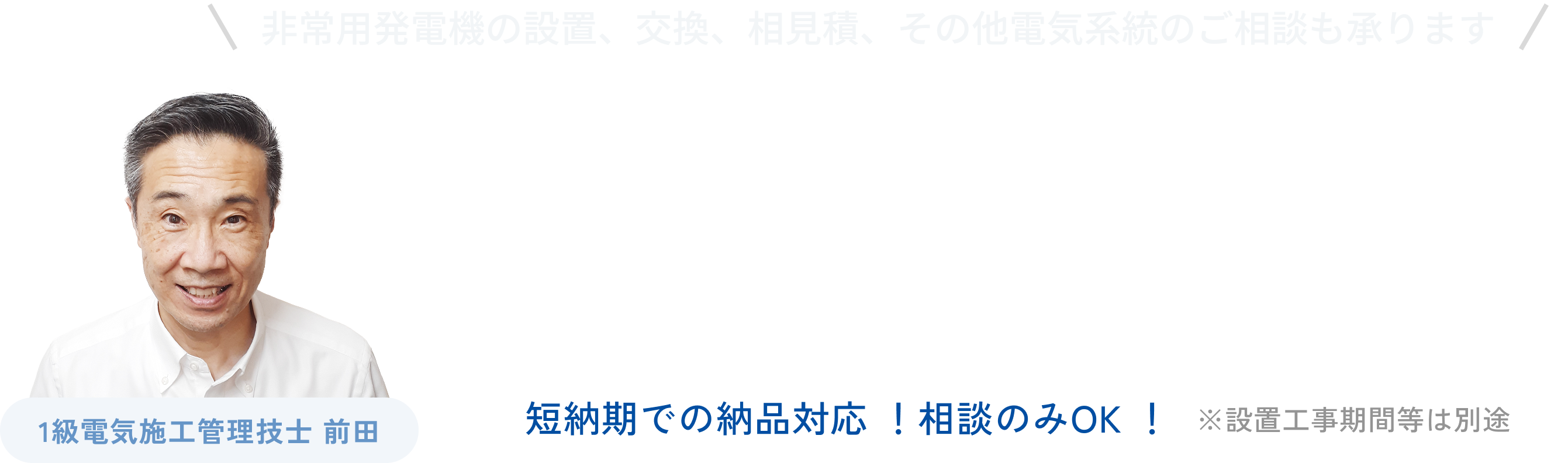
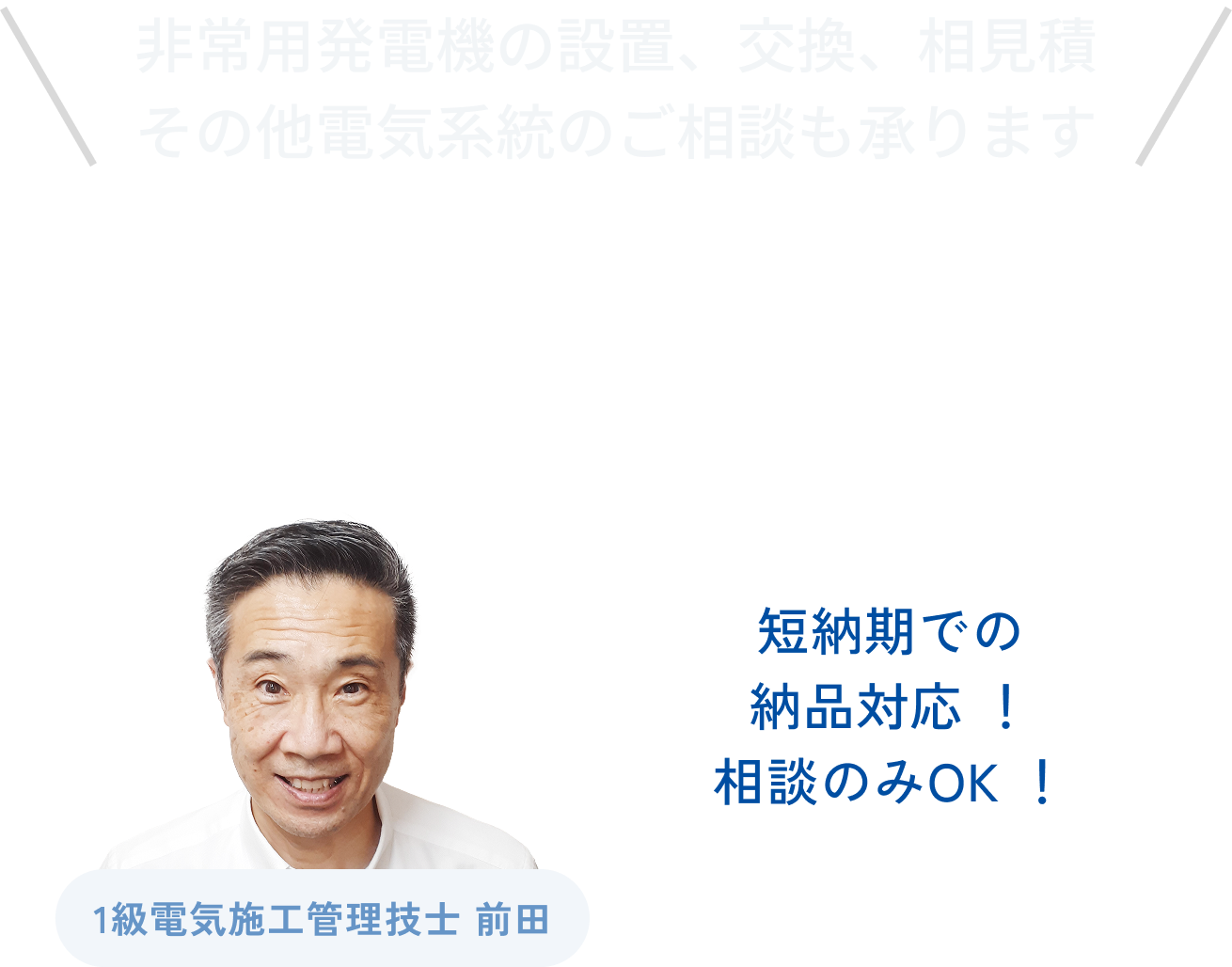
非常用発電機のサイズを決める要素
非常用発電機は災害時に電力供給を行う重要な設備であり、多くの施設に導入されています。非常用発電機にはさまざまな種類があり、そのサイズも多岐にわたります。
では、非常用発電機のサイズは一体何によって決まるのでしょうか?ここでは、非常用発電機のサイズを決める要素として次の2点について解説します。
- 定格出力
- 発電方式
定格出力
非常用発電機のサイズは、特に定格出力に大きく依存します。定格出力とは、機器が出力可能な最大の電力です。つまり、非常用発電機の定格出力は一度に供給可能な電力を指します。
これは非常用発電機の選定において重要な要素であり、接続したい機器・設備の負荷総量よりも多い定格出力を選ぶことが大切です。
非常用発電機のサイズは、定格出力に比例して大きくなります。非常用発電機には発電を行うエンジンと、その稼働をサポートする機器が内蔵されており、定格出力が大きいほどエンジンが大型化するため、非常用発電機本体も大きくなるのです。
目安として、オープン型ディーゼルエンジン式非常用発電機の定格出力別のサイズをまとめると下の表のようになります。こちらは一般的なサイズであり、実際のサイズとは異なる場合がありますので、詳しくはメーカーカタログを確認してください。
◆オープン型ディーゼルエンジン式非常用発電機の一般的なサイズ
定格出力 [kVA] | 一般的なサイズ [mm] | 重量 [kg] |
|---|---|---|
100 | 約2,400×900×1,400 | 約1,500 |
250 | 約3,200×1,200×1,600 | 約2,800 |
500 | 約4,000×1,400×1,800 | 約4,500 |
1,000 | 約5,500×1,600×2,000 | 約7,800 |
2,250 | 約6,800×2,000×2,400 | 約12,000 |
また、大型化するのは本体だけではありません。非常用発電機には冷却・換気などを行う付帯設備が併設されますが、定格出力が大きくなるほど、これら付帯設備の規模も大きくなります。本体の大型化と併せて、設備全体のサイズが大きくなります。
発電方式
非常用発電機には複数の発電方式があり、それに応じてサイズも変わります。病院や工場などの大型施設向けの非常用発電機は、概ね次の2種類に分類されます(小規模なものを含めればもう少し多くの種類があります)。
- ディーゼルエンジン式非常用発電機
- ガスタービン式非常用発電機
ディーゼルエンジン式非常用発電機
ディーゼルエンジン式は、非常用発電機の中で最も一般的なタイプです。内部にディーゼルエンジンを搭載し、シリンダー内で高温・高圧の空気にA重油(軽油90%に残渣油を混合したもの)または軽油を噴射・燃焼させ、その爆発的なエネルギーでピストンを動かして発電を行います。
ディーゼルエンジン式はさらに、機器が露出した「オープン型」と、金属製の外箱に収納された「キュービクル型」に分類されます。
オープン型は屋内設置向けのタイプであり、キュービクル型に比べて機器本体はコンパクトであることが特徴です。ただし、屋内設置のため高温排気用のダクトが必要になり、加えて、専用の電気室や防音対策を講じる必要もあるため、こうした付帯設備も含めると他のタイプと比較して非常に大型となります。
対して、キュービクル型は屋外設置を前提としていることが多く、防水・防塵構造を備えた頑丈な外箱に保護されています。この外箱がある分、オープン型と比べて機器本体は大型です。ただし、オープン型ほどの付帯設備は不要であるため、設備一式としてみるとオープン型よりも小規模となります。
ガスタービン式非常用発電機
ガスタービン式は、燃料を燃焼させて得られた高温・高圧ガスでタービンを回すことで電力を供給するタイプの非常用発電機です。使用できる燃料は灯油・軽油・A重油などの液体燃料に加え、LPガス・都市ガスといった気体燃料にも対応しており、選択肢が広いことが特徴です。
ガスタービン式の機器本体は、ディーゼルエンジン式と比較して小型の傾向があります。ただし、高温排気ダクトなどの付帯設備まで含めると、確保すべきスペースはディーゼルエンジン式よりも大きくなります。
発電方式別のサイズの指標として、定格出力500kVAでの一般的なサイズをまとめると下の表のようになります。こちらは非常用発電機本体のみのサイズであり、ディーゼルエンジン式(特にキュービクル型)が最も大きく、ガスタービン式は比較的小型であることがわかります。ただし、付帯設備まで含めたサイズはこちらから大きく変わるため、注意が必要です。
◆発電方式別の非常用発電機の一般的なサイズ
発電方式 | 一般的なサイズ | 必要な付帯設備 |
|---|---|---|
ディーゼルエンジン式(オープン型) | 約4,000×1,400×1,800 | 電気室、防音室、高温排気ダクト |
ディーゼルエンジン式(キュービクル型) | 約4,800×1,500×2,200 | 基礎 |
ガスタービン式 | 約3,200×1,400×2,000 | 高温排気ダクト |
非常用発電機のサイズに関わる注意事項
非常用発電機は、施設に適した定格出力や発電方式に基づいて選定することになります。結果的にサイズが大きい非常用発電機を導入することになった場合、主に設置時に注意すべきことがあります。最後に、サイズが大きい非常用発電機の設置時における注意点を解説します。
- 建物の健全性
- 搬入経路
- 点検スペースの確保
建物の健全性
まず注意すべきは、建物の健全性です。
非常用発電機のサイズが大きくなると、重量も一緒に増大します。屋内や屋上設置の場合、非常用発電機は専用の架台に支持されますが、架台の接地部に荷重が集中してしまいます。このままでは耐荷重をオーバーし、設置個所が大きく損傷する可能性があるため、該当箇所を補強する、もしくは荷重を分散するといった措置が必要です。
また、地震によって非常用発電機が転倒すると、機器そのものだけでなく、建物も損傷してしまうかもしれません。転倒を防ぐために、振動を吸収する防振ゴムやスプリングを設置、もしくはアンカーボルトや支持鋼材で固定するといった対策が取られます。
搬入経路
搬入経路も、注意すべき項目の一つです。
非常用発電機のサイズが大きいほど、搬入経路の確保が困難になります。他の設備が既に導入されている場合、非常用発電機の動線と重ならないよう回避させておく必要があります。
また、1,000kgを超える非常用発電機は、クレーンでの搬入が前提となります。設置作業の前に、クレーン車の道路使用許可取得や、警備員の手配などが必要になるため、施工業者と必要な手続きについて事前によく確認しておきましょう。
点検スペースの確保
点検スペースの確保も中止しなくてはならない項目の一つです。
非常用発電機には適切な点検スペースを設ける必要があり、これは消防法によって定められています。非常用発電機の種類や設置環境の条件によって確保すべき離隔距離は異なりますが、一般的に点検・保守作業のために必要な基本距離は0.6m以上とされています。
非常用発電機のサイズが大きくなるほど設置スペースの確保もさることながら、周囲のスペース確保が困難になります。しかし、これは安全を維持するために必要な措置であるため、確実にスペースを確保できるよう計画的に設置準備を進めましょう。
まとめ
非常用発電機は、災害や停電による電力遮断時に、必要な設備へ確実に電力を供給するための要であり、防災対策や事業継続の観点から幅広い施設で導入されています。サイズは定格出力と発電方式によって決まり、出力が大きいほどエンジンや付帯設備も大型化し、ディーゼルエンジン式は比較的規模が大きくなる傾向があります。
一方で、サイズが大きくなるほど設置に伴う課題も増えます。建物の健全性を保つための補強や荷重分散、クレーンを用いた搬入経路の確保、消防法で定められる点検スペースの確保など、設計段階から考慮すべき点が多く存在します。これらを怠れば、設置後の安全性や運用効率に大きな影響を及ぼす恐れがあります。
なお、今回紹介した数値はあくまで一般的な目安であり、実際には設置環境や施設の要件によってサイズや条件が変わる可能性があります。そのため、非常用発電機を導入する際には、専門知識をもとに総合的に判断できるプロの視点が必要不可欠です。
小川電機株式会社は、60年以上にわたり非常用発電機の設置工事から点検、修理、更新まで一貫して対応してきた実績があります。施設の特性や目的に応じた最適な提案と確実なサポートにより、安全性と事業継続性を両立する電力環境を実現します。
非常用発電機の導入や、既存設備のメンテナンスをお考えの方は、小川電機株式会社までお気軽にお問い合わせください。