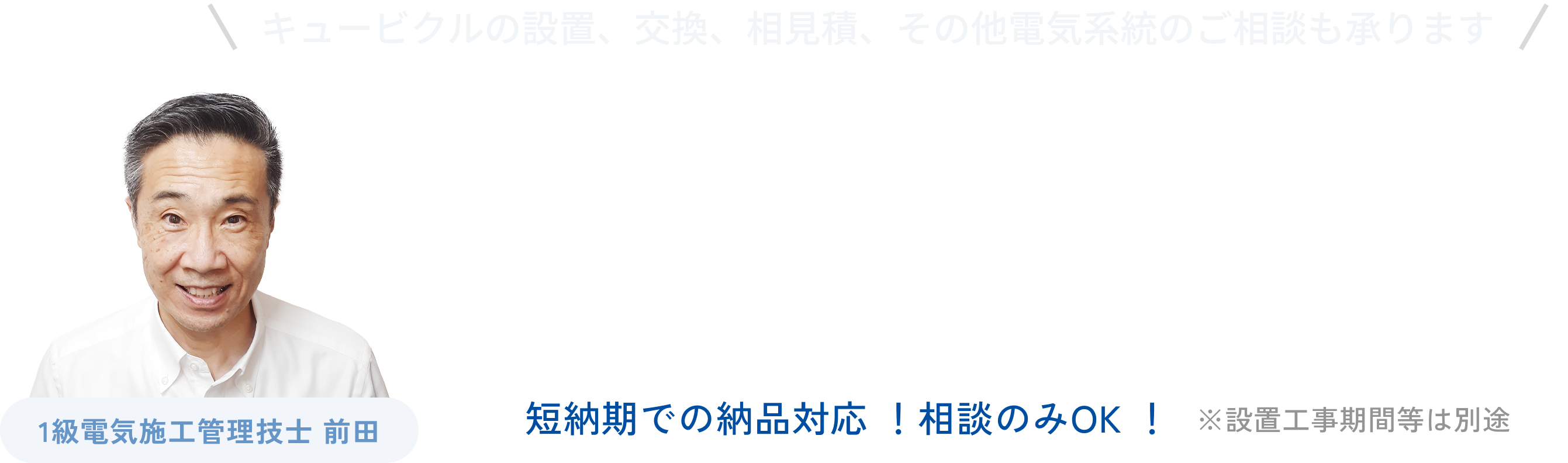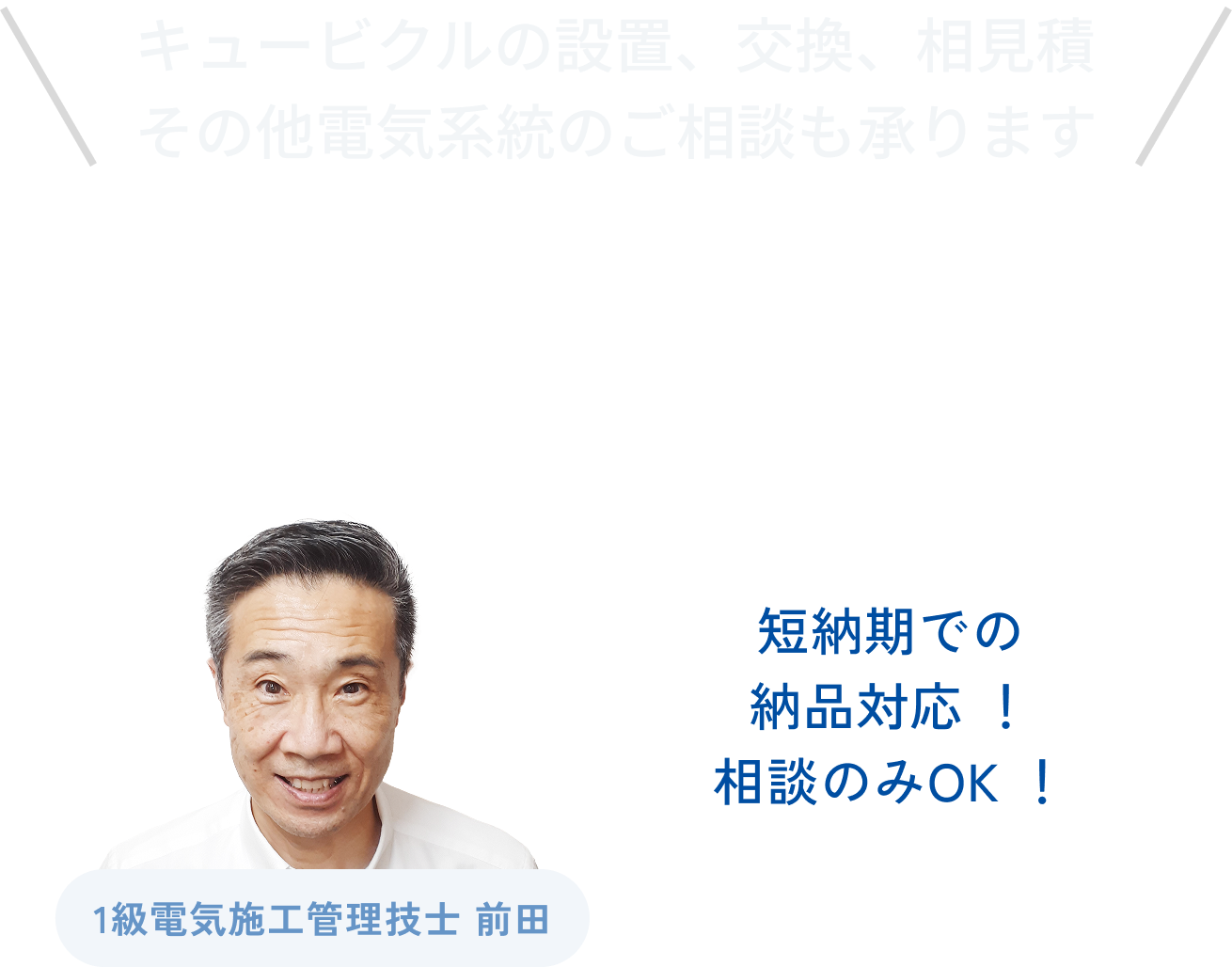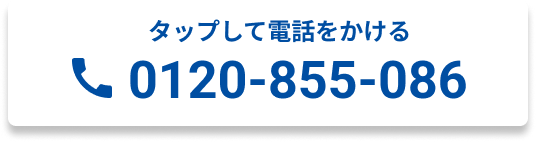キュービクルを屋外に設置する際には、屋内とは異なる法規や技術的な規定に従う必要があります。今回は、キュービクルの設置を検討している方に向けて、屋外設置時にとくに注意すべきポイントや関連する基準について詳しく解説します。設置環境によって守るべきルールが変わるため、事前に正しい知識を得ることが非常に重要です。
キュービクルの概要
キュービクルは、高圧電力を低圧に変換し、安全に供給するための重要な電気設備です。ここでは、キュービクルの基本的な仕組みと役割について解説します。
キュービクルとは
キュービクルは、高圧で送られてくる電力を施設内で安全に使用できるように変圧・制御するための設備です。発電所や変電所から供給される6,600ボルトの高圧電力を、商業施設や工場、店舗、オフィスビルなどの利用用途に合わせて、100ボルトまたは200ボルトの低圧に変換します。
キュービクルの役割
キュービクルの主な役割は、高圧で送られてくる電力を施設内で安全に使えるよう、適切な電圧に変換し供給することです。
発電所からは、送電ロスを抑えるために約6,600ボルトの高圧電力が供給されますが、そのままでは一般的な機器では使用できません。そこで、キュービクルを通じて100ボルトまたは200ボルトに変圧し、施設内の電力設備へ安全に届けます。
特に契約電力が50kWを超える商業施設や工場、オフィスビルでは、法令によりキュービクルの設置が義務付けられており、安定した電力供給と安全管理の観点から欠かせない存在です。
通常、こうしたキュービクルは建物の屋上や敷地内などに設置され、施設の電気インフラを支える中核設備として機能しています。
屋外にキュービクルを設置する際の基準
屋外にキュービクルを設置する場合、屋内設置とは異なる法的・技術的な基準に従う必要があります。ここでは、設置時に特に重要となる「保有距離」や「認定の有無」に関する基準について解説します。
保有距離の必要性
キュービクルを屋外に設置する際は、火災や事故を防ぐために、周囲の建築物との距離を一定以上確保する「保有距離」の確保が求められます。この設置基準は、『JEAC 8011-2014 高圧受電設備規程「1130-4 屋外に設置するキュービクルの施設」』に基づいており、さらに各自治体が定める火災予防条例によって、細かい要件が設けられている場合もあります。
JEAC 8011-2014 高圧受電設備規程「1130-4 屋外に設置するキュービクルの施設」
キュービクルを屋外に設置する場合の建築物等との離隔距離及び金属箱の周囲の保有距離は、次の各号によること。(火災予防条例(例)第11条)
①隣接する建築物または工作物、および当該施設が設置された建築物の開口部から、3m以上の距離を確保すること。ただし、隣接する建築物の一部が不燃材で造られており、防火戸などの防火設備が設けられている場合、または消防長が火災予防上問題がないと認めた構造である場合は、この限りではない。
②金属箱の周囲には、1m+保安上有効な距離以上を設けること。ただし、不燃材料の建築物で、防火戸などが設けられている場合は、「130-1(受電室の施設)」に準じて距離を保ってよい。
※保安上有効な距離とは、人が安全に移動できる範囲を指す。
これら設置の規定は東京都に限らず、他の自治体でも類似のルールが設けられている場合があるため、前には必ず事前確認が必要です。
参照元:Q100 キュービクルについての建築基準法,消防法ではどのような規制がありますか?(J-STAGE)
「認定キュービクル」と「非認定キュービクル」
屋外設置時に必要な保有距離は、キュービクルの構造によっては緩和されることがあります。特に「消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式受電設備」は、前述の距離基準を満たさなくても設置が可能とされます。
では、どのようなキュービクルがこの「支障がないと認められる構造」に該当するのでしょうか?JEAC 8011-2014では、次のいずれかに該当するものをそのような設備とみなしています。
- 消防庁告示第7号「キュービクル式非常電源専用受電設備の基準」に適合するもの
- 一般社団法人 日本電気協会の認定品または推奨品
日本電気協会の認定を受けたキュービクルは「認定キュービクル」と呼ばれ、そうでないものは「非認定キュービクル」と分類されます。
また、推奨キュービクルとは、日本電気協会が1969年に開始した制度に基づき、信頼性の高い製品として推奨されたものを指します。これは、感電事故や停電事故の防止を目的としています。
一方、認定キュービクルの制度は1975年の消防庁告示を受け、1976年に創設されました。この認定を受けたキュービクルは、消防検査の一部を省略できるといったメリットがあります。
推奨キュービクルは基準が緩やかな分、認定よりも取得しやすい反面、消防上の優遇措置は認定キュービクルの方が多く設けられています。
このように、認定または推奨を受けたキュービクルは、火災予防上の安全性が担保されていると判断され、「1130-4 屋外に設置するキュービクルの施設」の規定に基づく保有距離の確保が一部免除される可能性があります。
「屋内キュービクル」と「屋外キュービクル」の違い
屋内設置にも独自のルールがあり、屋外基準と混同すると是正指導の対象になりかねません。ここでは、JEAC 8011-2014 の屋内基準「1130-3」を中心に、屋外基準「1130-4」との相違点を整理します。計画段階で違いを押さえることで、設置スペースと安全性を最適化できます。
屋内設置時の必須保有距離
「1130-3 屋内に設置するキュービクルの施設」では、金属箱と周囲との間隔を1130-2 表に従い確保するよう定めています。主な数値は次のとおりです。
キュービクルの面 | 離隔距離 |
|---|---|
|
操作する面 |
0.6m以上 |
|
点検を行う面 |
扉幅(※1)+保安上有効な距離(※2) |
|
換気口がある面 |
0.2m以上 |
※1:扉幅が1m未満の場合は、1m以上を確保する必要があります。
※2:保安上有効な距離とは、人員の移動や作業に支障がない最小限のスペースを指します。
屋外基準との比較ポイント
屋外基準(1130-4)は建物から3m以上の離隔や「1m+保安距離」を求める一方、屋内基準は最小 0.2〜0.6m とコンパクトです。ただし、狭い分、点検動線が確保しにくくなるため、レイアウト設計と安全対策を十分に検討しましょう。
これらの距離は自治体の火災予防条例などで上乗せされる場合もあるため、最終判断前に必ず所轄への確認が必要です。
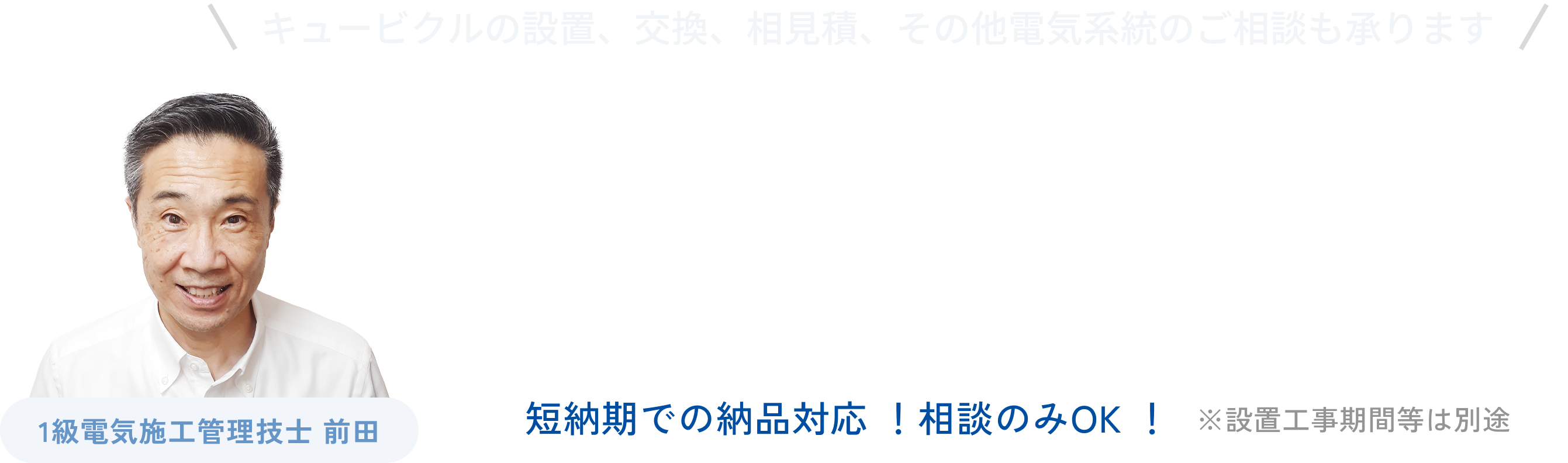
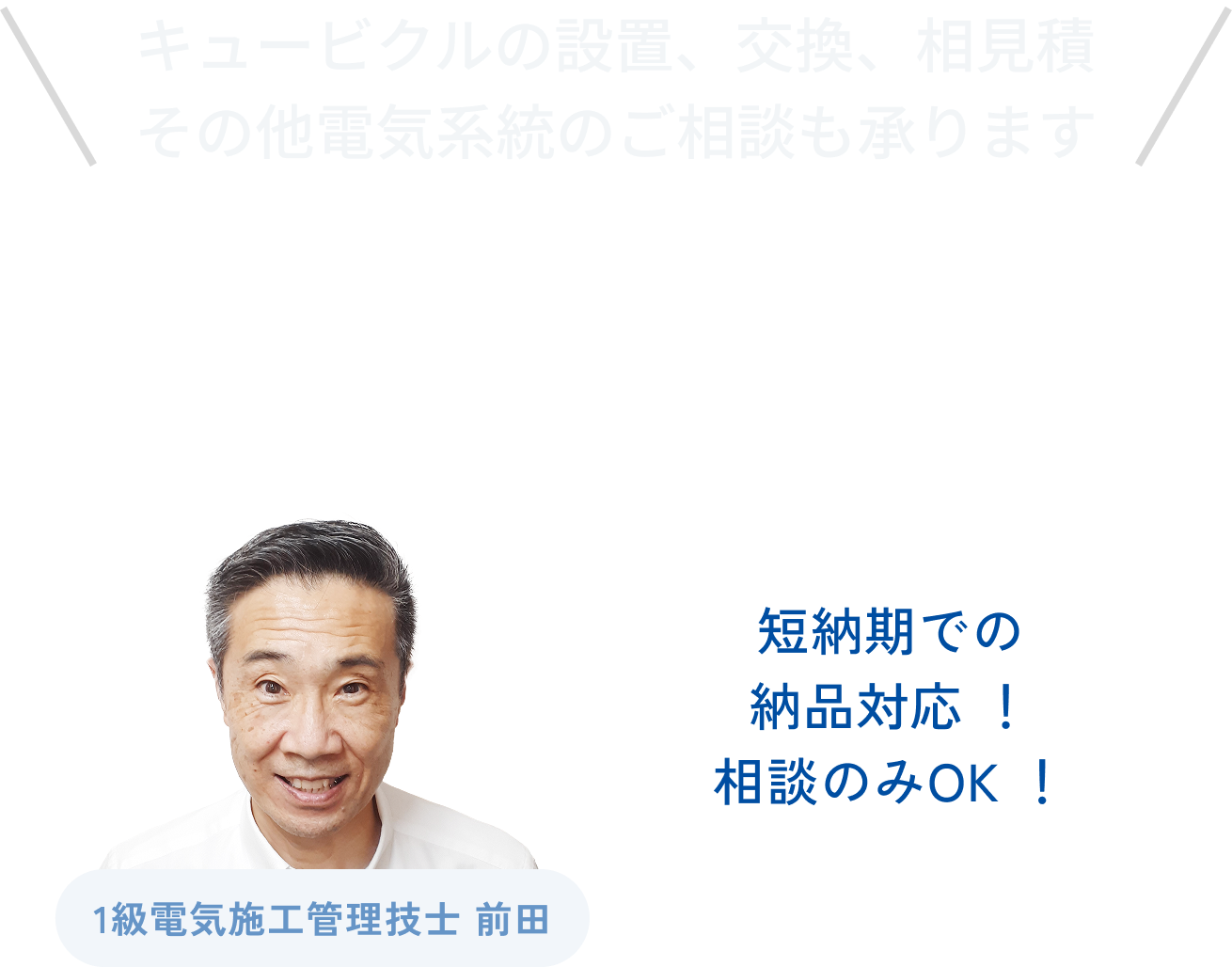
屋外キュービクルに関する法令
屋外にキュービクルを設置する際は、火災予防や建築基準、安全運用の観点から、複数の法律・条例・規程を遵守する必要があります。ここでは、代表的な法令や技術基準について具体的に解説します。
消防法
消防法では、政令で定められた条例制定基準に基づき、各市町村が火災予防条例を定めています。この条例では、出力20kWを超える変電設備の設置に関して、位置や構造、管理方法などを規定しており、キュービクルの屋外設置に直接関わる重要な法令の一つです。
火災予防条例
屋外にキュービクルを設置する場合は、各自治体が定める火災予防条例にしたがって、周囲との「保有距離」を確保しなければなりません。
この基準は『JEAC 8011-2014 高圧受電設備規程「1130-4 屋外に設置するキュービクルの施設」』でも明文化されています。
JEAC 8011-2014 高圧受電設備規程「1130-4」より抜粋
①隣接する建築物や工作物、または施設自体の開口部から3m以上の距離を確保すること。
ただし、建築物が不燃材料で造られており、防火戸などの防火設備が設置されている場合や、消防長が火災予防上支障がないと認めた場合は、この限りではありません。
②金属箱の周囲は、1m+保安上有効な距離以上を確保すること。
こちらも同様に、防火措置が講じられている建築物に隣接する場合は、「130-1(受電室の施設)」に準じた距離で設置可能です。
※保安上有効な距離とは、人が安全に移動できるための最小限のスペースを意味します。
参照元:Q100 キュービクルについての建築基準法,消防法ではどのような規制がありますか?(J-STAGE)
建築基準法
建築基準法そのものにはキュービクルに特化した条文はありませんが、電気設備としての設置には同法の安全・防火に関する工法規定に従う必要があります。
(電気設備)
第三十二条 建築物の電気設備は、法律またはこれに基づく命令により、電気工作物に係る建築物の安全および防火に関する定められた工法で設けなければならない。
参照元:建築基準法(e-GOV)
高圧受電設備規程
キュービクルは高圧受電設備に分類されるため、日本電気協会が定める「高圧受電設備規程」に準拠して設置する必要があります。特に屋外設置に関しては、「1130-4 屋外に設置するキュービクルの施設」にて詳細な規定が設けられています。
【JEAC 8011-2014「1130-4」より抜粋
■設置場所の選定
- 重量に対応できる堅固な地盤を選ぶこと
- 換気孔の位置を考慮し、風向きに配慮すること
- 屋上や狭い空間では、風雨・氷雪からの影響を避ける配慮が必要
■基礎に関する条件
- キュービクルの重さに耐える強度を確保すること
- 雨水が入った際の排水口を設けること
- 検針が容易なように、窓位置と高さに配慮すること
- 点検用の足場スペースや代替設備を確保すること
- 異物侵入防止のため、網やカバーを設置すること
■据付時の注意点
- 地震に備え、基礎に堅固に固定すること
- 床面は水平に据え付けること
■高所設置や人の接触リスクがある場合の対応
- 保有距離が3m未満なら、高さ1.1m以上の柵を設けること
- 幼児が触れやすい場所では、柵の設置が推奨される】
このように、屋外にキュービクルを設置するためには、複数の法令や技術基準をクリアする必要があります。安全性を確保するためにも、設置前には該当する法規を十分に確認し、自治体や専門業者と連携して進めることが重要です。
まとめ
キュービクルは、高圧で送電されてくる電力を施設で安全に使用できるように変換する、非常に重要な電気設備です。発電所や変電所から供給される6,600ボルトの高圧電力を、100ボルトまたは200ボルトといった低圧に変圧することで、工場や商業施設、オフィスビルなどの電気設備を安定的に稼働させることが可能になります。
設置場所が屋外か屋内かによって、保有距離や設置条件には明確な違いがあり、それぞれ「1130-3」「1130-4」といった高圧受電設備規程に基づいた対応が求められます。さらに、キュービクルが日本電気協会の認定品や推奨品であるか否かによっても、保有距離などの規定が一部免除されるケースがあるため、事前確認が不可欠です。
また、キュービクルの設置には、建築基準法、消防法、火災予防条例、高圧受電設備規程など、複数の法令や技術基準が関係しています。特に屋外に設置する場合は、基礎の強度や防水・防火対策、保守点検時の安全性まで配慮しなければならず、専門的な知識が求められる分野です。
キュービクルの設置をご検討中の方は、法令遵守と安全性を両立させるためにも、専門業者に相談することをおすすめします。
創業60年以上の歴史を持つ小川電機株式会社なら、キュービクルの新規設置から修理・点検まで迅速に対応し、トラブル発生時もワンストップで解決可能です。信頼できるパートナーとともに、最適な設置計画を策定し、安心・安全な電力インフラを実現してみてはいかがでしょうか?少しでもご興味をお持ちの方は、小川電機株式会社までお気軽にお問い合わせください。